「熊の駆除に反対するのは頭おかしい!」
「被害から見て熊を駆除すべきだと思う」
「熊の駆除がかわいそうって、なぜ?」
ネットのコメントを見て、上記のように感じた方は意外と多いかもしれません。
結論、熊を駆除するメリットは人命や農業を守れることだが、デメリットとして駆除のしすぎは生態系に悪影響を及ぼす可能性がある。
近年は、熊に襲われたという被害が増えています。
東北や北海道での被害が多いですが、東京都の高尾山や神奈川県の丹沢付近にも熊は生息しているため、東北や北海道以外に住んでいる方も関心の高いニュースになっています。
そこでこの記事では、熊を駆除するメリット・デメリットについて、分かりやすく解説していきます。
熊を駆除してほしい!熊を駆除するメリットとは?

結論から言うと、熊を駆除するメリットは、人命の安全を守れることと農業の保護です。
近年、ツキノワグマやヒグマの出没が急増し、住宅地や農村部で人との接触が頻発している現状があります。秋から冬にかけては、食糧不足の影響で熊が山を下り、人家周辺に現れるケースが多発しています。
特に東北や北海道では人里近くに出没する事例が後を絶たず、住民の安全や生活環境への影響が深刻化しています。
実際、熊による人身事故の件数はここ数年で急増しており、死亡例も報告されています。熊は非常に力が強く、突発的な遭遇が命に関わるケースもあります。もしも通学中の子どもや農作業中の高齢者が襲われれば、被害は取り返しのつかないものになります。
また、農作物や家畜への被害も甚大で、農林水産省の調査によれば、熊による被害額は年間数億円にも上り、地域経済への影響も無視できません。
トウモロコシ、果樹、ハチミツなどが標的となり、農家にとっては経済的打撃が大きいです。
こうした被害を未然に防ぐ手段として、駆除は現実的な対応策といえます。
さらに、熊は学習能力が高く、一度人間の居住地や食料にアクセスできた経験を持つ個体は、繰り返し出没する傾向にあります。熊が人間の生活圏に定着してしまう前に対処することで、「学習個体」が増えるのを防ぐ必要があるため、単なる追い払いでは対処が難しく、結果的に駆除という措置が選ばれています。
そういったことから「熊を駆除してほしい」という声が近年、全国各地で急増しています。
しかしその一方で、熊の駆除に強く反対する動物愛護団体からのクレームも根強く存在します。
多くのクレームは「命を奪うべきではない」「山に帰せばいい」といった倫理的な考えから出されています。特に都市部や自然から距離のある地域の人々にとって、クマは「野生のシンボル」のように映ることもあり、駆除に対する強い拒否反応が生まれやすくなっています。
もちろん、熊の命も大切です。そのため感情に任せるような無闇な駆除ではなく、個体ごとの行動履歴や危険性を見極めた上での駆除が必要です。それでも、最後の手段として駆除があり、行政も慎重な判断のもとで実施しています。
熊は本来、山林に暮らす生き物であり、自然界の一部です。山林の環境悪化やドングリなどの餌不足といった要因などによって人里に降りてきています。
山林の環境悪化については、森林の伐採や人間による道路建設や観光施設開発などにより、熊の生息環境が狭まり、生態系が崩れている現状があります。
熊の餌不足については、主な食料であるドングリやクリ、山菜、果実などが不作になる年があり、特にナラ類やブナ類の「マスティング」と呼ばれる自然現象で、数年周期で実のなりが悪くなる年があり、そのような年には熊の出没が顕著に増加します。2023年もドングリの大凶作が報告され、熊の出没件数が過去最多になった地域がいくつもありました。
※マスティング(masting)」とは、ある年に特定の樹木が一斉に大量の実(ドングリなど)をつけ、その翌年以降にはほとんど実をつけない、という周期的な開花・結実の現象のこと
熊が人里に出没する原因には、人間側にも原因があることを理解した上で、熊との共存を模索する必要があります。
熊の行動圏が人間の生活圏と重なり始めている今、熊がかわいそうと感じる一方で、命や生活を守る現場では、駆除という選択もまた避けられないという現実があります。
熊を駆除するのはかわいそう!熊を駆除するデメリットとは?

結論から言うと、熊を駆除するデメリットは、生態系への影響や動物愛護団体や市民から社会的な反発や対立が起こることです。
まず、生態系への影響についてですが、熊は山林の中で種子を運び、自然環境のバランスを維持する役割を持っています。こうした個体を安易に減らすことで、長期的に見れば森林生態系に悪影響を与える可能性があります。
仮に駆除によって熊が絶滅した場合、次のようなことが生態系に起こる可能性があります。
1つ目は、食物連鎖の崩壊です。
熊は雑食性であり、果実、昆虫、小型哺乳類、魚類などを食べることで、動植物の個体数を調整する役割を担っています。熊がいなくなると、熊が捕食していた動物の数が増えたり、逆に熊が食べていた植物の種子が拡散されなくなったりすることで、森のバランスが崩れるおそれがあります。特にサケなどを食べることで、山の栄養循環にも貢献しているため、これが途絶えると森林の成長にも悪影響が及ぶと考えられます。
2つ目は、森林の再生サイクルの低下です。
熊は果実や木の実を食べ、その種を糞とともに広い範囲にまき散らす「種子散布者」としての役割があります。熊がいなくなると、こうした種子の移動が減少し、特定の植物が広がらなくなり、結果的に森の多様性が失われていく恐れがあります。これは長期的には森林の更新力の低下にもつながります。
3つ目は、中型動物の増加による農作物被害の拡大です。
熊が絶滅すれば、熊に抑えられていたアナグマやイノシシなどの中型哺乳類が増加する可能性があります。これらの動物も農作物を荒らすため、熊の不在によって別の被害が拡大するという「負の連鎖」が起こるかもしれません。結果として、農業被害が減るどころか増える可能性も否定できません。
また、社会的な反発や対立もデメリットの一つです。
熊の駆除に対しては、動物愛護団体や市民から抗議が殺到することもあり、行政や地域社会が批判の矢面に立たされることも少なくありません。そうした摩擦は、地域の信頼関係や行政運営にも悪影響を与える可能性があります。
熊の駆除を巡って行政・地域社会と動物愛護団体や市民との間で摩擦が生じ、行政運営や信頼関係に悪影響を与えた事例があります。
■札幌市(2023~2024年)
札幌市では住宅街や市街地近くで出没したヒグマを駆除し、即日報道発表しましたが、国内外から100件以上(2024年)のメール・電話が寄せられ、多くは批判でした。2023年7月には約600件の意見が集中し、中には「君たちはいつも殺してばかりだ」といった感情的な攻撃もあり、行政担当者は非常に苦慮したとされています。
■北海道・雨竜町(2024年6月)
熊の駆除を公表後、多くの抗議が殺到し、業務が麻痺しかけたため、その後、駆除公表を控える判断を取っています。
クレームによって上記のようなことが起こると、本来、市民のために必要だった業務が行えず、新たな問題が発生してしまうことが考えられます。
最後に、熊の駆除は一時的な被害防止にはなっても、根本的な問題の解決にはつながらないという指摘もあります。
例えば、山の中に十分な餌がなくなったことが人里への出没の原因であるなら、環境改善や植生の回復こそが必要です。駆除だけに頼れば、根本的な原因が放置されたままになり、同様の問題が繰り返される恐れがあります。山に熊の餌が無くなった状況を解決するには、自然環境の回復と人間活動の見直しが鍵になります。
熊を駆除する判断は決して軽いものではなく「かわいそう」といった感情論や倫理観と人命を守るといった安全対策の狭間で揺れる複雑な問題を抱えています。
熊の駆除に関するSNSの声
ここでは「熊の駆除」に関するSNSの声を紹介いたします。
Xでも熊の駆除に対して「反対するのは頭がおかしい」「動物愛護団体は狂ってる」といった内容の投稿が多かったです。
秋田県の佐竹敬久知事の発言からも、熊の苦情に対するクレームや抗議に対して「それはおかしい」といった思いを持っている方が、SNSでは多いように感じました。
熊の駆除は、熊の出没地域に住んでいる方の人命を守る、農業への被害を抑えるという役割がありますが「熊の命を大切にしろ」といった倫理観からくるクレームや反対が多くあるのも事実です。
人の命も熊の命も守れる対策を引き続き見つけていくことが、共存するうえで重要になり、期待されています。

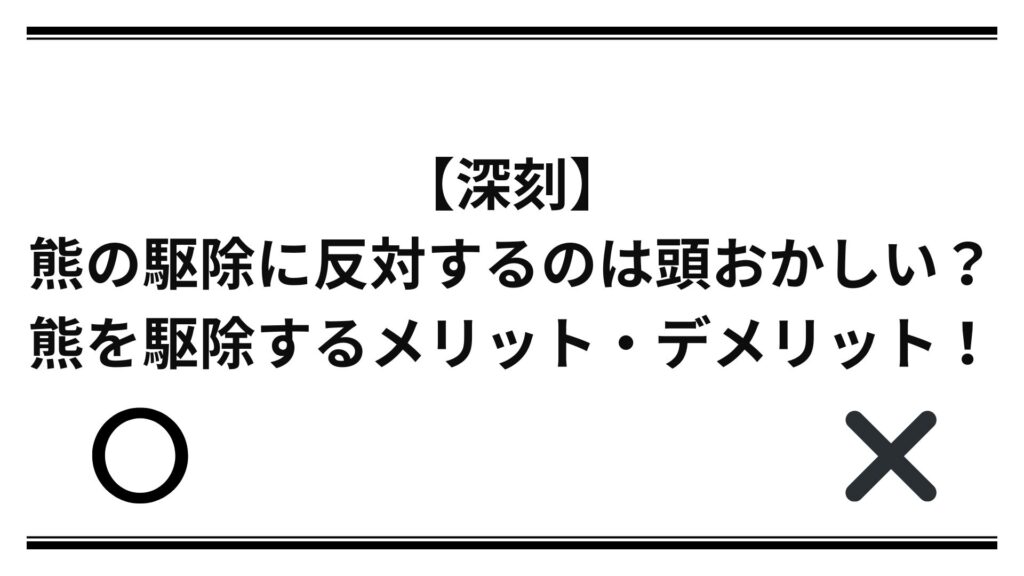

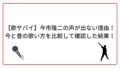
コメント